子育てをしていると、
「なんで私ってこんなにできないんだろう」
「さっき子どもにあんな言い方しなきゃよかった…」
と、自己嫌悪に陥る瞬間ってありませんか?
たとえば――感情的に怒ってしまったとき、家事や育児が全然思い通りに進まないとき、SNSでほかの家庭を見て落ち込んでしまったとき…。
親なら誰でも「やっちゃったな」と思う場面は日常の中にたくさんあります。
そんな気持ちから抜け出すヒントをもらうべく、小学校教員を経て、教育系会社運営と子どもの第3の居場所をつくるべく学び場(フリースクール)の運営している教会の方にインタビューを行い、牧師先生の教えも踏まえて答えていただきました!
1. どうして親は自己嫌悪に陥りやすいの?
子育てをしていると、つい「できて当たり前」と思い込んでしまうところがあります。
でも、考えてみてください。
バイオリンをいきなり持たされて「はい、弾いてください」と言われても、弾ける人なんていませんよね。子育てもそれと同じ。経験ゼロから始まるんだから、最初からうまくいかないのは当然なんです。
しかも子どもを育てる経験なんて、多くても4人分。つまり、4回しか練習できないんです。そんなに少ない練習でプロみたいに上手にできるわけがないんですよね。
それなのに「うまくできるはず」と思ってしまうから、できなかったときに自己嫌悪に落ち込みやすいんです。
本当は、“初心者で当たり前”。
子どもから学んで、少しずつ“親になっていく”ものなんです。
そして、つい他の家庭と比べてしまうのも自己嫌悪のもと。
でもね、根本的に大事なのは「自分の価値を知ること」。
誰かと比べる必要なんてありません。あなたは子どもにとって唯一の親。もうその存在だけで、十分すぎるほど価値があるんです。
2. モヤモヤ…自己嫌悪にはこんな影響も
もしその気持ちが長く続いてしまうと、自分自身がどんどん疲れてしまいます。
そして「責める」思考回路が固定されてしまうと、近くにいる子どもにまで向いてしまうことがあるんです。これが怖い…
親にずっと責められていると、子どもは「自分はダメなんだ」と思い込みやすくなってしまう。自己肯定感が下がって、良いところを見つけるよりも「嫌なところ探し」をしてしまうようになるかもしれません。
でも逆に言えば――子どもにとっても良くない!と思うと、子どものためなら、と親も変わることができる気がしませんか?
3. 感情に振り回されないためのヒント
親が自己嫌悪に陥る代表的な場面のひとつは、子どもにイライラしてしまったときじゃないでしょうか。
「つい怒ってしまった…」「また感情的になった…」と、自分を責める気持ちが出てしまうこと、ありますよね。ここからは、そんなネガティブな感情とどう向き合うか、具体的なヒントを見ていきましょう。
子ども相手にイライラしてしまったあとって、すごく自分が嫌になりますよね。
「もう怒らない!」って思ったのに、また怒ってしまう…。でも怒らないようにする方法を言われても、正直無理じゃないですか?そんな方法を教えてもらっても現実的じゃない。
ここで知っておいてほしいのは――怒りはそもそも完全にはコントロールできないということ。
体と心は別物です。怒っちゃうときは怒っちゃうんです。
でもね、10回怒ったうち、1回でも抑えられたら、それはすごいことなんです。
「今日はちょっと頑張れたな」って自分を褒めてあげていいんです。
ここでは、「怒らない」ではなく「怒りの感情を減らす」コツを紹介します!
怒りを軽減するための準備が大事
・予測を立てる
イライラのタイミングって大体決まっていますよね。朝の支度、出かける前、子どもが思うように動かないとき…。そのタイミングをシミュレーションしておくと良いです。感情も事前に想像していると、「あ、来たな」と思えたら、ちょっと冷静に対応できるようになります。インフルエンザもワクチンを打つことで発熱したときに熱が上がり過ぎないようにするのと同じで、ワクチンを打って怒りの免疫を付けるイメージです。
・良いところを見る習慣を持つ
子どもをよく観察して「いいな」と思える部分を意識して見つけていくと、不思議と行動の見え方が変わります。気になるところだけじゃなく、いいなと思えるところも見つける。一つの出来事を多面的に見る癖がつくと、感情が爆発する前に立ち止まれるようになります。怒りの感情は出ちゃうとは思いますが、その時に、目の前の子に「何が起きているんだろう?」「時間がないからと手伝うと叫んでうるさいけど、自分でやりたいという気持ちが出てきたのか、成長!」というように子どもを観察して変化を良く捉えたり分析したりしていると、落ち着いてきます。
4. 負の感情から抜け出す習慣
夫婦で分け合う
「自分だけが子育てしている」と思うと負担が大きくなって、子どもの小さな行動にもイライラしやすくなります。
夫婦で「負の感情」も分け合えたら、気持ちが軽くなるんです。
ある先生はこうおっしゃっていました。
「植物を育ててみなさい。自分が水を飲む時に、あ、植物に水をやらなきゃ、と思い出すように、夫婦もお互いに神経を使いながら育んでいくんです。」
最初のデートを思い出すのもいいかもしれませんね。夫婦の関係を手入れしていくことも、自己嫌悪から回復する力になるんです。
問題を分解する
自己嫌悪の正体は「問題が大きく見えすぎている」ことが多いです。
先生はこんな話もされていました。
「問題は裂いて考えなさい。大きい木にいきなり火をつけられないけれど、小さく裂いて薪にすると簡単に火がつく。問題も同じで、細かく裂いていくとどこが問題か見えてくる。」
つまり、全部をごちゃっと「できない」と捉えるのではなく、因数分解するように整理することが大事。すると、自己嫌悪の理由もはっきり見えてきます。
「10割問題がある」と思っても、実際は8割くらいは問題じゃないことが多い。
むしろ、すでに解決していたり、できていたりする部分もたくさんあるんです。そうしたら自己嫌悪に陥る必要はなかった!と気づけることもあります。
おわりに
子育てで自己嫌悪に陥るのは、あなたが一生懸命やっている証拠。変わらなきゃ、変わりたいと思っているからこそそのように悩んでいるんだと思います。
でも「できなくて当たり前」「親も子どもと一緒に成長していけばいい」と思えたら、少し気持ちが楽になります。
そして、子どものためにも、自分を責めすぎないことが大切です。
親が自分を認められると、その姿を見た子どもも「自分を好きでいていいんだ」と感じられるからです。
思い通りにいかない毎日の中で、できなかった自分を責めるより、「ちょっとできた」自分を認めていきましょう。
それが、子育てを少しでも軽く、温かくしていく一歩になるはずです。



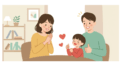
コメント